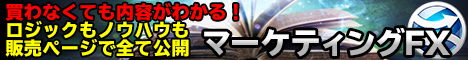明治限定品から新作まで
✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼••
車椅子に乗っている彼との
日常を綴っています


▷▶︎▷
✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼••
(介助者がいる私たちの日常って?)の続きです*°
私はもともと別の介護派遣事業所で訪問ヘルパーをしていました。
そのときの訪問はもちろん障害の程度にもよりますが、1日に合計3時間くらいで、例えば
8:00~8:30 30分 トイレ介助と朝食づくり
10:00~10:30 30分で トイレ介助と体位交換
12:30~13:15 45分で トイレ介助と昼食づくり
18:30~20:00 90分で入浴介助と夕食づくりとトイレ介助と車椅子からベッドへの移乗
というふうに、訪問時間と、介護内容が決まっていました。(数人のヘルパーで上記をローテーション)
ご縁で自立生活センターに出会って、見守り・待機を含めた24時間の自立生活の介助者となりました。
もともとは上記のような訪問介護をしていたので、最初は24時間もヘルパーがいて何するんだろう?そんなにすることあるのかな?って思っていました。
ときには、『結果的に』なにもしていない時間もあります。でもこの『結果的に』というのがとてもとても大切なのです。
もともと私が働いていた一般的な訪問介護の場合、、
起きたくても起きたくなくても8:00~8:30の間は起きてなきゃいけないし、
10:00~10:30の間に排泄しておかなければ、体位交換しておかなければ12:30までチャンスはない…
18:30~20:00 の間にお風呂に入らなければ、それ以降に入浴はできないし、ベッドに入らなければ、翌朝まで車椅子のまま…?
すべて自分の生活を計画通りにしなきゃいけないんですよね。
外出だって、前もって計画しておかなければできません。
(もちろん障害も程度によるので、ここでは介助者がいないと様々なことができない人、と考えてください。)
でも、24時間介助者がいれば、起きたい時間に起きることができるし、排泄だってしたくなったらすればいいし、入浴だって自分の決めた時間に入ることができる。
1時間ぼーっとしたいときは介助者にその旨を伝えてぼーっとすればいい。
コンビニの肉まんが食べたくなったら買いにいけばいい。
そして、疲れて朝ゆっくり寝たいときは寝たいだけ寝ればいい。
自分の生活を自分で組み立てていくことができるのです。
✎︎____________
介助者になって、
「フレンチトースト食べたいからつくって」と夕方の16:00に言われたときに。
前の仕事で訪問して訪問してた人たちは、16:00にお腹が空いたらどうしてたのかなぁ。。って初めて考えました。
もちろん、私たち健常者だって、いつもいつもしたいことをしたいときにできるわけではありません。
でもできるけどしない、というのと、できないのは全く違う。
食べようかなぁ~って思えるのと、はなから食べれないのは全く違うことだなぁって思うのです。
お腹すいたな、なにか食べようかな
冷えたな、お風呂に入ろうかな
天気がいいな、外に行こうかな
今日は夜更かししようかな
私はこの「いつでも思いつく自由がある」ことにとても感動したのを覚えています。
小さなことだけれど、とてもとても大きな自由だと思います。
そして質問を頂いたのですが
介助者は無償のボランティアではありません。
もちろん制度が整っていない時代はそうでした。
今話題のこのこの映画
の主人公、鹿野さんもボランティアを集めて生活をされていた人です。
でも、それは制度が整っていなかったときのこと。
本来はボランティアではなく、この生活は保障されるべきことなんですよね。
ボランティアは自力か周りの人たちによって集められることになると思います。
声を出せる人はいいけれど、周りが積極的に集めてくれる人ならいいけれど、鹿野さんのように人間的魅力がある人ならいいけれど、、、
そうじゃない人はどうなるのでしょうか?
ボランティアを募っています、と声が出せない人の生活は?
周りも助けて、と言えない人の生活は?
どんな人でも、どんな状態でも、生きていく権利があります。だから、制度であるべきなのです。
そしてボランティアはやっぱりあくまでボランティアで、ボランティアの来れるときに…というボランティア主体の生活になる可能性をはらんでいます。
なので、自立生活センターの事業の一環として、自立生活センターの理念に沿った介助ができる事業所をもっているのが通常です。(小さな団体はまた別の方法もありますが、それはまた)
そこの事業所から派遣されて、そこから私たち介助者はお給料を頂いていますよ*°
✩ ⋆ ✩ ⋆ ✩ ⋆ ✩ ⋆ ✩ ⋆ ✩ ⋆ ✩
最後に、りょーたくんが一昨年書いた記事を載せます。
私たちがこうやって笑って一緒に過ごせるのも、運動をしてきた人たちがいて、制度をつくり、そして守り抜いてきた先輩方のおかげです。
自立生活あってこその、結婚生活。
私たちのライフスタイルがどんなふうになっていくかはまだまだ未知数だけれど────
介助者さんに理解してもらいながら、3人の心地よい生活をつくっていけたらいいなぁと思います。
長くなりましたが読んで頂きありがとうございました(*´ `*)
(関係ないけど、明治安田生命のcmに応募してみた写真。笑)
いとしさと切なさと明治
以前に天龍寺に行った時に途中で見つけたお寺です

帰って調べたら…
おおさか十三仏霊場の第十七番札所でした
改めて近鉄奈良線額田駅へ

重願寺 【 じゅうがんじ】
當知院本誓山重願寺と号し、大阪都市計画の谷町線拡張により昭和37年に現在の額田に移転した浄土宗のお寺です。
総本山は京都の知恩院。豊臣秀吉の本願で、文録3年(1594)5月18日に岸譽雲海上人が開基しました。現在の住職は19世忍譽行雄です。
山門
しっかりとした山門やぁ〰️

あれ…
入れない…

って隣が開いてて一安心

本堂
御本尊の木造阿弥陀如来様は座像で像高140センチ、頭高46センチ、膝張108センチで、その姿は木彫全金色で定印を結び、船形光背を負い、重蓮台に座して藤原時代の特徴を残してるとの事…

2階建ての本堂…
下は洋で上は和…

なんで…
こないなったのか…

多寶塔
日本一小さい多寶塔らしいですよぉ

おまつりしている聖観音様は立像で高さ105センチ、お顔は温和で藤原様式の優美な観音様です

この観音様は大坂三十三ヶ所観音めぐりの第17番札所として江戸時代以来信仰され、近松門左衛門作『曾根崎心中附り観音めぐり』の中にも『17番に重願寺、ここからいくつ生玉の、本誓寺ぞと伏拝む』と重願寺の事が記載されてるんやって

十三重塔
天高くそびえ立つ姿は圧巻ですよね

桂塚明治時代西成区天下茶屋にもとの桂塚があったのです
この塚は自然石に漢文で落語家桂一門の流れを書いた塚で、昭和15、16年くらいまであったのは確かでその後倒れて埋まってしまったのか今も行方不明だとか
重願寺の碑は本来の塚がなくなったので「建てよう」ということに賛成した上方と東京の落語家の名前が碑の裏に刻まれています
平成9年5月12日、3代目故桂米之助、桂文福さんが5代目文枝さんを連れて紫綬褒賞受賞記念、落語家生活50年記念に参詔されたんやって
本堂の横に…
こちらが本堂の入り口かな…

閉まっていて中が見えん…

凄い石仏やぁ〰️

顔が…
めちゃ有難い石仏なんやと思うんやけど…
なんか…

お地蔵様

いろいろな石仏があるお寺で楽しいです

下から見たら
本堂と
多寶塔が綺麗に見えたぁ〰️
あっ!
だから本堂は2階建てになってるのかな…

違うかな…

山門から見た大阪平野です

生駒山からの眺めめちゃいいよ〰️

夜景は最高だろうなぁ…
デート…

今回のランチは近鉄奈良線、
瓢箪山駅から南へ
商店街に入ってしばらく歩いたところにあるのがこちら花まるキッチン森田だぁ〰️
この辺りでは肉といえば森田っていうほど有名で、周辺に関連するお店が数件ありますよぉ 店内は落ち着いた和の雰囲気漂う上品な掘りごたつ席が並び、清潔感があってとてもいいお店でしたぁ
店内は落ち着いた和の雰囲気漂う上品な掘りごたつ席が並び、清潔感があってとてもいいお店でしたぁ
1日10食限定
国産牛ステーキ御膳1380円だぁ〰️
1日10食限定ってめちゃ最高やん
それに…
食べログでクーポンが発行されていて…
1080円で食べれるのだぁ〰️
このボリュームで1080円ってヤバくないですかぁ〰️

自分で焼きながらいただくお膳なので、自分のペースで焼いていけるのがいいよなぁ〰️
肉…分厚くないですかぁ〰️

肉質はやわらかくジューシィーでかなり美味しかったぁ〰️
タレは…
おろしポン酢、ワサビ醤油、塩です
小鉢に春雨とキュウリの酢の物、サラダはキャベツに葉物とポテサラをあしらったものです
味噌汁はワカメの味深仕上げです
ご飯は白ご飯と炊き込みご飯が選べて…
白御飯ならおかわり自由だぁ〰️
瓢箪山駅から徒歩2分
瓢箪山駅から99m
大阪府東大阪市神田町2-7
40代から始める明治
今回から奈良若草山の山焼きの紹介です。
2019年1月26日に見物に行きました。
この若草山の山焼きは典型的な神仏混交
の行事です。若草山(わかくさやま)は、
奈良県奈良市の奈良公園の東端に位置
する標高342m、面積33haの山です。
山焼き前の若草山です。下図②からの撮影です。
ピンクの番号順に歩きました。
最初は歴史から
若草山山頂には古くから知られる鶯塚古墳
(前方後円墳)があり、「鶯山」とも言われます。
また、菅笠のような形の山が三つ重なって見
えることから俗に「三笠山」とも呼ばれます。
山焼きの起源は、鶯塚古墳から出る幽霊が
人々に災いをもたらすという迷信がありまし
た。また、1月頃までに焼かないと災いをも
たらすと言われました。なので通行していた
人が放火していました。再三に渡り、この火
が東大寺境内に迫る事件が起きました。
右上に鶯塚古墳があります。(グーグルより)
1738年12月に、奈良奉行所は若草山に
放火停止の立て札を立てました。しかし、
誰かが放火を続けていました。
隣接寺院への延焼の危険が絶えなかった
ので、江戸時代末期頃には、東大寺・興福寺
と奈良奉行所が先手を取って、立ち会って
山焼きをするようになりました。このために、
東大寺と興福寺が寺領の境界争い防止のた
めにやったという誤解も生まれました。
夜間に行なわれるようになったのは明治時代
後半からです。
なので山焼きの起源は、鶯塚古墳に葬られ
た人の、霊魂を鎮める供養だったようです。
上図①の東大寺南大門です。
鹿と外国人観光客が多いです。
顔がかゆいようで擦っていました。
牡鹿ですが角を切られています。
露店がたくさん出ていました。
せんとくんがいました。
いつの間にか結婚して子供が出来たようです。
今日はここまでで、明日に続きます。
読者募集中ですので、
希望があれば、相互登録します。
毎日午後8時半頃に更新しています。
「相手わかるように」に設定して読者登録してください。
読者のブログ村・ブログランキングは出来るだけ押しに行きます。
Ctrlキーを押したままで、ポチしたら画面が飛ばされません。
お手数ですが、よろしく。
 ぽちっと
ぽちっと
 押すだけ
押すだけ
お願いします。
![]()
![]() ぽちっと
ぽちっと![]()
![]() 押すだけ
押すだけ